ドイツ旅行の話に入る前に、もう一度「睡眠」について書いておきたい。
私は睡眠・食事・運動・休養の順に大切だと思っているが、とにかく睡眠だけは健康状態・病気の種類・生活環境・個人差(嗜好)に関係なく誰にとっても重要だと思っている。
私が‘うつ’を得て以後、より睡眠時間を増やしたり質を高めたりするのに効き目があった方法をお知らせしておく。
まずは呼吸だ。これなら、いつでも誰でも出来て費用もかからない。睡眠以外でも、気持ちが高ぶり過ぎ・落ち込みすぎ・焦っている等のストレス多めの状態を平常に近づけるには一番簡単で即効性がある。必ず鼻から、出来るだけ肺が満タンになるまで吸い、ほんの数秒止めた後、基本的に口からゆっくり時間をかけて吐き出す。これだけでも良いのだが寝床に入ってからやる時は数を数えながらだと、余計な事などを思い出す余地が減り、呼吸に集中しやすくなる。一例として「1・2・3・4で肺に溜め込み5・6・7は止める。8で吐き始めて(だと覚えやすい)そのまま15まで数えながら肺が空っぽになるまで吐き切る」←私はこの呼吸法を何度か繰り返す事で、一時期すごく寝つきが良くなった。ただし今は合わなくなったのか必要なくなったのか分からないが、この方法は使わずに済んでいる。とにかくリラックスするための一つの手段なのであまり真面目にやる必要はないし、自分に合う形にアレンジするのもいい。様子を観ながら1~2週間ほど試してみてほしい。因みに口呼吸は極力やめて鼻呼吸の癖をつける事。特にこの季節は口を開けたままだと乾燥するし病気をもらいに行ってるようなものだ。鼻炎持ちの人などは、まずその症状を治す事を優先した方が良い睡眠に繋がる(それが簡単じゃないから困ってる、という事も分かるのだが)。
次にやった方が良いのが運動だ。といってもジム等に行く必要はない。私のように長期間患っている者に必要なのは「暮らしていく」為の体力と筋肉だ。当然それは普段の暮らしの中で身に付けられるはずなのだ。しかしこれから書く事は、やる気がある時だけ・やる気がある人だけでいいと思う。意欲が湧かないのに無理に頑張ってやってはいけない。私のやり方はある程度、症状を自力で抑えられる人・体力が戻っている人向けであって、まぁまぁハードルが高い。というのも私はもう1年近く洗濯物を手洗いしている。最初は電気代節約の為だったが、どー観ても洗濯機より汚れ落ちがイイし達成感がある。「手洗いで洗濯する」作業はやってみると分かると思うが、とにかく「シッカリ何度も絞る」のが大切だ。おかげで腕の筋肉が付き握力もだいぶ戻って来て自分の身体を自分の物に出来ているという自信・実感が出て来た。とはいえ仕上げには洗濯機の脱水機能で済ませるし、洗濯物が多くて面倒な時・寒くて手洗いが嫌な時・シーツなどの大物を洗う時などは洗濯機に任せて、少しずつ慣れて行けばいい。
そしてもし、やる気がない人や体力が戻っていなくて自信を失っている人でも、何かのタイミングを見つけて、ハンカチ一枚・靴下一足から洗ってみるというのはどうだろう。健常者からみれば、ほんの些細な下らない事かもしれないが、私達精神疾患を持つ者はとにかく委縮して何から手を付ければいいのか分からなくなってしまっている。とりあえず「自分の衣類を自分で洗う」なら失敗しても、少なくとも他人に迷惑をかける事はない。一番身近な小さな事からコツコツとやっていくしかないし、小さな事が出来るようになってからでなければ、本格的な運動の為に自力で外出する等、それこそ出来るはずがないのだから。
次は寒い季節に必要な快眠グッズについてだが、やっぱり私はコタツがないと生きて行けない。「見た目がやぼったい」「掃除のとき面倒」「一度入ったら出られない」など非常に御尤もな意見もあるが、やはり「電気代が安い」「エアコンよりは入手しやすい」「足を確実に温めるので入眠しやすい」などの精神疾患持ちで費用を抑えたい向きには利点が多い。「コタツで寝ると風邪をひく」という声もよく聞くが、私個人の意見としては、あれは子供やお年寄りなど体温調節機能が万全でない人にみられる傾向だと思う。少なくとも私は20年以上コタツが原因で風邪をひいた事はない。「あんたみたいに身体が頑丈な人ばかりじゃない」と言われてしまうと返す言葉がないが…。
快眠グッズもう一つは「湯を入れたペットボトル」だ。もう既にやっている人も多いと思うが、これも費用が掛からず誰にでも今すぐ出来るところが良い。使い捨てカイロは非常に便利だが、ゴミを減らせて低温火傷の心配もいらないので、私個人としては断然ペットボトル派だ。不便なのはあまり熱くない湯を入れるのでせいぜい1~2時間しか持たないのと、蓋をシッカリ閉めないと大変な事になる点だが、ありがたい事に今冬は一度も使わずに済んでいる。
言いたい事が多すぎてなかなか本題に入れないが、睡眠についてもう一つだけ。
私のように子供の頃から身近な人との関わり方が上手くいかなかったタイプというのは、思っている以上に大勢いる、と最近つくづく思う。ほとんどの人は自覚がないか、大っぴらに言うべきではないと考えているから認識出来ないままになっているのだろう。つまり私を含め「子供の頃の辛い体験が想像以上に長期に渡って人格形成に影を落とす」事に気付いていない人も大勢いる、という事だ。そしてまた大人に成りさえすれば人間関係が上手くいくなんて事もあり得ない。生きている以上、人間関係での悩みは尽きる事のない泥沼なのだ。だからこそ私達は睡眠不足に悩み続けるしかない。
このままでいいのだろうか?という迷いの最中にいた3~4年前、しょっちゅう頭の中をグルグル回り続けていた歌詞がある。「♪3歩進んで2歩下がる」と「♪探すのをやめた時見つかる事も良くある話で」の2つだ。1つ目には「いやいや2歩どころじゃねぇわ、100歩も1000歩も後退しまくってんだよコッチはっ」と当時は(頭の中でだけ)反発し続けていたし、いま考えてみてもある程度健康な人に通用する歌詞だなと思う。2つ目には「それは確かにそうなんだよね…」と賛成しておく以外の思考力は当時は持ち合わせが無かったが、今では、この歌詞に対しては「全く、その、通りっ」と納得させられている。
つまり何が言いたいのかというと今一度「自分の睡眠」を振り返ってみてほしい。どういう環境(暗さ・室温など)・寝具が眠りやすいのか、眠る前にはマイナス思考を避け楽しい事を思い浮かべるとか、自分のできる範囲でいいのでアレコレ試して研究・選択してほしい。上に書いた私のやり方はあくまで参考に過ぎない。そうして色々手を尽くした上で、それでも眠れなかったら、その時は「睡眠をスッパリ諦める」「睡眠に執着しない・拘らない」←これが本っっっ当に難しいし、こうして書いている自分も辛いし、とにかくしんどかった。それでも実行するしかないし、私は睡眠が改善されたと実感できるまで2~3年程かかったと思う。私の場合は最低でも一晩3~4時間は眠れたし最長でもそれが3日程度だった。どんなに苦しくとも4日目には倒れこむように爆睡できたので、ある意味まだ楽な方なのかもしれない。ひどい場合は一睡もできないまま一週間という患者もいるだろう。でも疲れが溜まれば眠れる日は必ず来る。そうして睡眠を全力で探究しながら、同時に諦めるという無理ゲーを毎日毎日毎日毎日続けていく。本当に苦しいが精神疾患を持っている者は基本的に強い人間が多いので、何とか無事にやり遂げてほしい。もちろん仕事は休めるなら無理せず休むという選択も出来るだけ活用してほしい。
ここからはドイツ旅行の続きを。
約30年前、ブランド品に興味がなく外国旅行初心者の日本人がドイツを観光する場合の基本コースはほぼ決まっていたといって良い。城と教会と美術館・博物館の類、そして偉人の生家・終の棲家といった所が定番だと思うが、私も友人も、その辺りに関しては「田舎者のおのぼりさん」的な固定観念に縛られていて、観光とはそういうモノだと思い込んでいた。もちろんそういった観光名所も現地でなければ観られない物だし、どれも一度は観るべき価値のある芸術・文化であるのは間違いない。だが人間というのは、やはり興味の薄い物に対しては集中力や記憶力が働かないのだ。一応「写真撮影可」なら取りあえず撮っておこうと考えるが、旅行中に味わった珍しさ・感動も、せいぜい帰国して現像に出した写真を見る時くらいまでだろう。日常生活に戻って一ヶ月もすれば、すっかり過去の思い出になってしまい、次に写真を見返すのは3年後か5年後か10年後か。旅行なんてそんなもんだ、と言ってしまえばそれまでだが、やはり20万円ほどの金額を出してわざわざ買った「経験」だし、普段の暮らしの中で、その「経験」を無駄なく活かしたいと考えるのは貧乏性が過ぎるだろうか。
第10綴(その1)の後半に「自分の手足と頭を使った不便な旅がしたい」と書いてしまった。あの表現でも間違いというほどではないが、こうして3ヶ月に渡って書いていく内に少しづつ思い出して来た事がある。私が異国を旅行して一番知りたいと思っていたのは、「一般庶民の普通の生活・価値観・考え方」だった。
このブログを読んでいるのは、当然ながら普通の日本人がほとんどだと思う。その「普通の日本人」であるはずの、このブログを読んでいる読者の皆さんは「普通」って何だろう?と考えた事がある人はどのぐらい居るのだろうか。
私は高校を卒業して働き始めた頃から、少しずつ漠然とだが不安を感じるようになった。高校在学中にも薄らと違和感はあった様な気がするが、ほとんど意識していなかった。しかし働くようになって、日常的に交わされる「普通それぐらい出来るでしょ」とか「それ普通じゃないよ。変だよ」とかの会話が、何についての、どの辺の基準で成り立っているのかが、さっぱり分からない。
当初、私はこんな基本的な事が分からないのは、自分がイジメられていたせいだと思っていた。「普通」という‘普通’の言葉が分からないのは、小学校・中学校と「普通」の人間関係が築けていなかったからではないか、と心配になり始めた。かといって面と向かって人に訊くのは恥ずかしいし何か違う気がする。そんな時に折よく外国旅行に誘われた。だったら他の国の人を見ていれば何か参考になるかも、と考えたのだ。
ドイツ鉄道に関する知識・利用方法などは全てドイツ好きの友人が受け持ってくれた訳だが、初めて乗るのだから分からない事もあったし失敗もあった。
うろ覚えで記憶違いの部分もあるかもしれないが、おそらくベルリンからミュンヘンまでの長距離を寝台車などではなく背もたれもほとんど倒せないような普通の座席で一晩かけて7~8時間乗りっぱなし、という方法でドイツ鉄道を利用した事がある。この歳になって思い出すと「若さって怖い」としか思えないが、こんな無謀な計画を実行に移してしまった当時の私達も、この行程が最もキツイという事にはもちろん気付いていた。かなり緊張していた、とも思う。
早めに駅に着いて少しでも落ち着けそうな座席を確保しようと考えたのは当然の判断ではあったが、そこで、ほんの小さな問題を起こしてしまった。私達は早めに列車に乗り込んでいたのだから始めは乗客はかなり少なく、このくらいならゆったり乗れる、と安心していた。
だが発車時刻が近づくにつれ、当然ながら乗客は増えて来る。乗り込んでくる人々(ほぼ全員白人)で俄かにざわつき始めた車内で「私達、ものすご~く目立ってる?」等と落ち着かない気分で座っていたのだが、ふと気が付くと、若い男性二人が私達が座っている席のすぐ脇に立って、こちらを見ている。そして私達に向かって何か話しかけて来たのだが、当然ながら言葉が分からない。それから、その男性二人が互いに何か二言三言やり取りをすると、隣の車両に移動して行った。「何だったんだろう?」と思いながらも特に気にも留めずにいたが、少し経ってから友人が「あっここ、もしかして予約席かも」と声を上げた。
私は何となく勝手に日本のローカル線の感覚で乗っていたので‘予約’の意味が分からなかったが、友人が「確か予約の場合は座席の上だか脇だかに予約者名が表示されてるって本に載ってた」と言うので、念のため座席の廻りをよーく見てみると、…確かにあった。日本の新幹線で言うと荷物棚の下側に当たる部分に、名前の様な文字が書き込まれた、タバコくらいの幅の厚紙が表示枠に差し込まれている。「こんなの見えねーよ」と思ったが、コチラの不注意には違いない。
私は取りあえず男性二人が移動して行ったらしい方向へ行ってみたが、相手の特徴など覚えていないし、もう発車時刻直前で満席となった車内にズラリと並んだ異国の人々の顔立ちが見分けられるはずもなかった。私はすごすごと友人の所に戻って来るしかなかった訳だが「せっかく譲ってもらったんだから有難く座らせてもらおう」と言う友人の意見に同意して腰を落ち着ける事にした。
友人が言うには、予約と言っても座れる席を確保する為だけの事前連絡であって、日本のグリーン車の様に別料金が発生する訳ではないらしいと聞いて多少はホッとしたが、…こういう時は何ともいえない居心地の悪さを感じるものである。(う~ん、やっぱり金銭は絡んでいないと思い込みたい後付けの記憶の可能性もある。30年経って後悔しても何の意味もないが)
なんにせよ、いくら若くても勝手の分からない外国の列車に一晩、腰掛姿勢で乗り続けるという方法は、全くお勧め出来ない。こんな無茶を真似する者はいないと思うが。
初めに書いたように私達はお決まりのコースを巡っていた。ガイドブック等をめくっている時は、どの観光名所も見ごたえのある・一見の価値のある珍しい場所・展示物であるように思うし実際そうなのだ。どこへ行くにもわくわくしながら出掛けて行ったし、当然見に行って良かったと思う物ばかりだが、基本的に城は武骨な石造りで、展示されているのは鎧と刀剣類が多いし、教会のステンドグラス等の美しさや荘厳な雰囲気も日本では体験できない。しかし城も教会も大きく高さがあって重厚感・圧迫感が強く、また戦争と宗教は流血の歴史でもある。階段しか無いので自分の足で上がるしかないし、上を見上げる動作も増えるので、意外と首が疲れる。城も教会もそれぞれ2か所ほども見れば、よほど強い関心や体力自慢などを兼ね備えていない限り、3か所目以降は「もういいや」となる。
…よく考えたら日本の寺社仏閣も同じような物だ。寺社の手前にはやたらに長い階段・参道があったり天守閣に上がるのも「階段というより梯子だな」と思うくらい急な造りになっている。どんな国も地位や権力を守る為には知恵・工夫・体力が何より必要で、異国でも同様に建造物の大きさや階段の多さに苦心・努力の跡が表れていると思うと何とも面白い。
現在の階段はだいぶ緩やかになっている、どころかエレベーターやエスカレーターの時代になり、知恵・工夫・体力は相当弱くなっているとしか思えない。
私達は本当に進化していると言えるだろうか。便利になればなるほど退化していると感じるのは私だけだろうか。
あ~~、また脱線してしまった。ドイツ観光に話を戻そう。
私は芸術方面は全般的に素養がないし全くの不得手だが、音楽は普通に聴くし絵を観るのも嫌いではない。しかし日本人というのは、何やらもったいぶって上品ぶって教養があるようなふりをして、演奏会とか美術館とか博物館に行く雰囲気が未だにあるような気がする、何となくだが。
少なくとも30年前のドイツの美術館・博物館にはそういう雰囲気が全くなかった。世界的に有名な画家の作品が並んでいるというのに、休憩用に置いてある簡易ソファに座り込んだままノートに向かっている人がいて、てっきり写生でもしているのかと思ったが、絵には一度も目を向けないまま、ひたすら何か文字を書き続けていた。他の客に迷惑をかける事もなく展示品を傷付けようとする訳でもないなら、入館料さえ払っていれば何をしていようが自由だよな、と思った記憶がある(とゆーか私も絵を観るより人間観察の為に入館料を払っていたような…笑)。
これは、また別の日だったと思うのだが、なぜか交通博物館の様な所にも行った。行ってはみたものの、よほど興味がなかったのか断片的に機関車・自動車・飛行機などが展示されていた事だけを覚えている。
興味はなくても来たからには写真くらいは撮っておこうと撮影可かどうか確認しようとしていると来館客らしい若い男性が「どうかしました?」といった感じで話しかけてくれた(私の記憶違いで、自分から話しかけたのかも知れないが興味のない物の為に自分から職員でもない人に質問する可能性は低い)。私はカメラを持ち上げながら「Camera ok?」と言ってみた。これで十分通じるだろうと思っていた。しかし男性はキョトンとした感じで、どーにも要領を得ない。次に「Flash ok?」と言ってみた。…これも通じないようだ。次にカメラの前面を指差して「パシャ」とか「カシャ」とか言ってみたが、反応がない、というより言葉として受け取られていない感じだった。この時以降「擬音語というのは日本語独特の文化なのかも」と考えるようになった。…というか、ああいった状況で完全スルーされるとビミョ~に恥ずかしい、という事の方が印象に残っているが。
しかし、そんなやり取りをしている内に、次に何を言えばイイのか分からなくなるし、正直もう写真が撮れるかどうか等どーでもよくなって来ていた。「もういいですから。お時間とってスミマセン」と言いたいのだが、途中から、また別の女性客も加わり「いやいや、遠慮しないでハッキリさせましょうよ」といった雰囲気になってしまっている。
どーしたものかと迷いながら、要はフラッシュの別の言い方があれば良いんだなと気付き「…ストロボじゃぁ通じる訳な(←モチロン日本語)」まで言った途端、唐突にあっさりと場が和やかに、というか拍子抜けした空気になった。最初の男性が「ここは館内全て写真は大丈夫ですよ」的な事を言っていたような気がするが、よく覚えていない。というか本気で写真など、どーでもよくなっていた。当時の私には「フラッシュが通じなくてストロボは通じる」というのが、どーしても釈然としなかったのだ(←どこまで言葉に拘ってんだよ…)。
直後、ほんの2~3人が興が醒めた様子でス~ッと離れて行っただけで、その場は急に静まり返り、私と友人だけがポツンと取り残されている光景は、正にくだらないコントの結末のようだった。
旅も終盤に差し掛かり、ドイツ南部から北上してケルンへ向かう辺りで、欧米系の夫婦らしい二人連れと、何度か連続して鉢合わせした事があった。
あの周辺は、首都フランクフルトが近いせいか、ケルンの大聖堂が観光地として人気があるのか、よく分からないが、人の往来が急に増えていた様に思う。そういう場所では、大抵考える事は皆一緒なので、特に‘縁があった’とかではなく、単純に偶々タイミングが合っただけのよくある事なのだろうとは思うが。
これも記憶が定かではないが、最初は列車の乗降口とかで「先どうぞ」「ありがとう、ではお先に」くらいのやり取りをしただけだったと思うが、2度目か3度目くらいに、その日泊まった宿でばったり顔を合わせた時には、日本人同士でなくとも、ふいに知り合いに会ったような感覚で4人とも笑ってしまった。私達二人は(第11綴・その2にも書いてあるように)例の観光案内所で紹介してもらった宿なので、同じ【i】で、その夫婦とも入れ違いになっていたのかもしれない。
そして最後に鉢合わせしたのは、その宿の最寄りの駅のトイレの前だったと思う。私が先に用を済ませ交代して、友人がトイレに行っている間、二人分の荷物の番をしながら傍にあったショーウィンドウの様な物をのぞき込んでいた。すると例の夫婦の奥さんが一人でトイレから出て来るのが目に入った。と言っても私が奥さんを見たのは、のぞき込んでいるショーウィンドウのガラス越しに、である。つまり奥さんの方では、私が奥さんに気付いているとは思っていないのだ。とっさに私は、このままでいたら奥さんがどう反応するのか観てみたい、と思ってしまった。お互いに旅行者という立場は一緒だし相手が悪い人間でない事も分かっている。それでも鉢合わせが4回目ともなると、さすがに愛想笑いするのも面倒くさくなって来る。相手が日本人でない場合どういう反応をするのか確認するには絶好の機会である。(←私はこーゆー姑息というか小癪というか、ひねくれたやり方にあまり抵抗がない。決して褒められるような行動ではないのも分かっているが)
で、その奥さんはどうしたか?私の後ろ姿を見て、すぐに気が付いて立ち止まり、ちょっと迷いながら周囲をキョロキョロと見回してから2~3秒間、何か考えている様子だったが、私に声をかける事は無く、すぐに夫君が待っているらしい方向へ小走りで駆けていった。
突然だがここで、この項の書き出し部分に戻らせて頂く。
私も普段何気なく使っている「普通」という言葉。正直、未だにこの言葉の意味は分からない。だが「普通」の基準は確実にある。ものすごく曖昧で不透明で非常に分かりにくい形をしているが間違いなく存在している。今のところ私の考える「普通」という言葉の意味が分かりにくい原因は、性別によって年齢によって国によって時代によって環境によってその場の雰囲気によって「普通」という言葉を発した当人の背景によって微妙に形や基準が変わるからだと思う。極端な言い方をすると「普通」という言葉は非常に重要な意味を持つと同時に、全く意味のない言葉でもある、という事だ。
大半の読者は私が何を言いたいのか理解できないと思う。私も何を言いたいのか、自分で理解できていない部分がかなりある。だからこそ、この言葉の意味を今後も考え続けていこうと思う。
では、なぜ、このタイミングで、こんな文章を差しはさむ必要があったのか?
あの奥さんは、自分の「普通」を弁えていた。ガラス越しに観察するという少々‘すれた’やり方ではあったが、おかげで体裁や忖度などの余計なものを挟まずに素の「普通」を観る事が出来た。そしてその「普通」は、私の「普通」とも、かなり似通っていた。国籍や、おそらく環境・背景も違う、全く別の人間なのに、あの10秒間ほどで、私の「普通」は他の人にも通用すると確認する事が出来た。
「自分を知る」という表現で分かりづらければ、「自分に合う自分を選んでいく」と言い換えても良いのかもしれない(…やっぱりまだ分かりにくい、というかますます分かりにくいか・苦笑)。
今回は‘脱線’が多くなってしまった。だが、次の出来事でドイツ旅については最後になる。
帰りの飛行機に乗る前日に、必ず済ませなくてはならない用事があった。私達の利用したのはかなり安い航空チケットだったが、帰りの便に乗る前にリコンファーム(予約再確認)の手続きの為に航空会社に電話する必要があったのだ。
旅慣れた人なら、どーってことない電話連絡なのかもしれないが、私も友人もどちらかというと人見知りするタイプだし、英語しか通じないと旅行会社から聞いていたので、やはり電話を前にして緊張していた。
友人は直前まで自分が電話するべきと思っていたようだったが申し訳なさそうに「ちょっと私無理みたい。頼んでいい?」と疲れた表情を見せていた。私ももちろん疲れてはいたが、ふとドイツに向かう機中で「友人が疲れた時は自分が積極的に動こう」と考えていた事を思い出した。
もう旅も終わるのに今ここで動かなかったら、もう機会は無いぞ?と自分を奮い立たせて「うん。私やってみる」と、まだ余裕があるような雰囲気を無理やり醸し出しながら、チケットに印刷された電話番号を押していく。ドキドキしながら電話に出た相手に「リコンファーム プリーズ?」と思いっきり日本語寄りの発音で言ってしまった。もう既に英語っぽく発音する気力など無くなっている。
相手は何か英語で話し始めたが、私はいつの間にか無意識に「え~っと、ワンスモアプリーズ?」等と言ってしまったのかもしれない。急に相手が何かを察した様に「Are you japanese?」と訊いてきたので「イエス、ジャパン…」と返すと、少し間が空いて「お電話代わりました。日本語で大丈夫ですよ」と聞こえた瞬間は安心と嬉しさで泣きそうになった、などと書いては少々盛りすぎかもしれないが。
いま思い返してみても、あの旅行は面白かったし、収穫が多かったし、心底行って良かったと思う。
もうあれ以上、意義のある旅は、2度と無いような気がする。

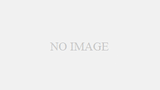
コメント