前回のドイツ旅は書いていて楽しかったし、忘れていた記憶の中に、思い出せて良かったと思える事が幾つもあったので、とても有意義だった。しかし文章作成が楽しければ楽しいほど、書き終えた後は「次は何を書けばいいのだろう…」と毎回途方に暮れている。
去年の年末には、年明け1月に何を書くか、一応決めていたテーマはあった。しかし、さて書くかという段になって急に、いま書くべきではないような気がしてしまったので、そのテーマは一旦保留とし、別の話題を練り直すのに、2~3日余計に掛かってしまった。しかも途中から、これまで一年間に書きそびれていた箇所を見つけてしまって、アレもコレもと思う内に何とも、まとまりのない内容になってしまった。ブログはもちろん日常のあらゆる決断は自分の「なんとなく、こうした方が良いような気がする」という非常に言葉では表現しづらい「感覚」でやっている。
脳みその中の「正常な部分」と「‘うつ’の部分」とが拮抗しているのを感じる。「正常部」が「‘うつ’部」をうま~く選り分けようとしているのだが、選り分けすぎても‘うつ’を表現できない。このうまく行きそうで、なかなかすんなり行かない状態に、イライラしつつも楽しいと思っている自分もいる(完全にM気質・笑)。
私は30代初めの頃に、比較的大きめのぎっくり腰を1度やっている。経験者なら分かると思うが、とにかくアレは体をど~動かしても腰に痛みが走り固まってしまって、にっちもさっちも行かない状態が数日間は続くというのが最もツラい症状だ。そしてそのツラい症状を軽減するには、どんな処置が一番適切なのか、迷った経験のある者も多いと思う。特に冷やすべきか温めるべきかの2択は、現在のネット情報を観ていても未だに決着が付いていないようだ。
しかし当時の私は運のいい事に、すぐに分かり易い情報が手に入った。それは「冷やして楽になればそれで良いし冷やすのが良くないと思ったら温めてみる」という非常に単純明快な方法だ。しかし当時はPCやネットの知識は持っておらず、おそらく職場の人に聞いた民間療法的な情報で「ホントにそんなんでいいのか?」と少々疑いながらではあったが、素人の私にも納得できる方法だったし、整形外科に掛かれば大抵は炎症を抑えるための冷湿布薬を処方されるので素直にその指示に従っていた。
しかし3日ほど経つと冷湿布を張り替えた時のホッとする感じが薄まって来て、そのうち何も変化を感じなくなった。そして5日目辺りから冷湿布を張った瞬間「なんかイヤだ怖い」と感じたので、すぐにその湿布ははがして、風呂に入るようにしてみた。すると今度は温めた方がグッと楽に感じるのだ。「人間の身体って不思議によく出来てるな~」と感心したのを覚えている。そこからは割と早く回復していき、発症から10日と掛からずに仕事に復帰した、と記憶している。自分の「感覚」で判断して正解だった一例だ。
繰り返しになるが、私は医師ではないし上に書いたのは私個人の経験であって誰にでも当てはまる訳ではないはずだ。また、私自身の「自己判断」で失敗した例も数えきれない。特に「腰」の場合は椎間板ヘルニアなどが隠れている場合もあるとの事なので、やはり一度は、多くの症例を知っている・経験を積んだ医師に診てもらうべきで、その指示に従った方が早期に回復する確率が高い。しかしケガや病気で苦しんでいるのは、当然ながら患者本人であって、痛みの程度・変化を実感し症状が始まったきっかけから全ての経過を知っているのは患者本人以外には存在しないのだから、やはり患者自身も自分の「感覚」を信じて自分の状態を冷静に観察し、医師に報告・相談しながら治療を進めるのが最善であるのは間違いない。
ちょうど1年前に書いた第3綴「拘り」では非常にえげつない文章を書いてしまった。
脳みそが、やっとまともに近づいてきたと思える現在の「感覚」で思い出してみると、去年の今頃は‘うつ病’特有の“無謀”と“無神経”がかなり残っていたのだなと思う。何しろ気さくな人格者として誰からも慕われた稀代の名優の演技にダメ出しをしているのだ。病状が軽くなっている現在なら、畏れ多くて、とても書ける内容ではない。ブログ記事として書いた事を後悔はしていないが、あれから新聞の切り抜きを整理したり、何かの番組などで、カメラ目線の写真などが視界にいきなり飛び込んでくると、笑顔であっても(というか笑顔だと尚更)ぎくりとして思わず目を逸らしてしまう(←意外と小心者)。
しかしこの「感覚」は私一人の頭の中での空想・妄想であって、あまり意味はないのかもしれない。私の経験では、少なくとも相手が生きている人間の場合「きっと相手はこう思ってる」は、かなりの高確率で間違っていた。つまり私の‘気にしすぎ’の部分が多いという事だ。まぁそうは言っても、相手がもう‘この世’にはいないとなると、やっぱりぐだぐだと考えてしまうものなのだが。
私は基本的には霊感というモノは持っていない。しかし‘うつ病’がじわじわ進行していた時や負の連鎖から抜け出せずにいた時には、少々変な物を目にした事もある。
一度は、テレビの旅番組で一人の男性タレントが海岸沿いを歩いている映像を見ていたのだが、なぜかその男性の上半身に黒い影が掛かっていた。黒い日傘でも差しているなら問題ないのだが、その人は肩にショルダーバッグを掛けてはいるが、手には何も持っていない。なのに頭から胸にかけて暗く日差しがさえぎられているような状態で、顔がはっきり見えなくなっている。その時は「テレビが壊れた?…だったら影が動くはずないし。テレビ局が映像に加工でもしてるのかな?こんな事して何の意味があるんだ?」とは思ったが、そのうち忘れてしまった。その後、その男性が3ヶ月もしない内に急病で亡くなったと報じられてから、アレは死相だったと気が付いた。
もう一つは、時期がよく思い出せないのだが、テレビに出ている、ある俳優がゾンビにしか見えない時があった。ホラーでも何でもない、普通の現代ドラマだったと思うし、結構知名度のある人なので本来端正な顔立ちなのも知っているのだが、ドロドロに皮膚が削げ落ちた骸骨の顔にしか見えないのだ。しかし、その俳優は、その後も数年はドラマなどに時々出ていたし、いつの間にか骸骨に見える事もなくなり、美しい顔立ちに戻っていたので「あ~良かった。この人は死なずに済みそうだな」とホッとしていた矢先に、自殺と報道された。
断っておくが、上に書いたような事は4~5年に一回程度だし、ここ数年は変な物は見ていない。たぶん私は体力的にも精神的にも、そして運なども比較的強い方なので、ただ「見える」だけで済んでいるのかもしれない。なんとなくの「感覚」だが、ストレスが多い状態が長引いたり、病気で気持ちが弱ったりしていると、変な物が“するり”と入り込むという事は現実には起こり得ると思う。いわゆる「狐憑き」というヤツだ。実際に見た事がある訳ではないので証明も説明も出来ないし、具体的な対処法も分からないが、せめて「睡眠・食事に注意し体力をつける」だけでも十分効果はあると思う。「健全な精神は健全な肉体に宿る」のだから。
こーゆー“話題”には色々と、ご異見のある方も多いとは思うが、無料で誰でも読める私のブログであり、何を書こうが私の自由という事で、“ご笑読”頂きたい。
何年も他人と関わって来なかったので、つい忘れていたが、私には他人の性格や内面を判断するための指標のようなモノがある。あくまでも「私・ぬえのなくよ」視点での合うかどうか・関わっていくべきかどうかの判断基準なので、私以外の人では使えない部分もあると思うが、取りあえず書いておく。
長年かけて少しずつ構築して来たモノなので、かなり多岐にわたっており、細かい事を言い出すと切りがないのだが、現時点で書けそうなのは「自分の父親・母親を尊敬している」とか「家族の誕生日を大切にしている」という意味の事を知り合った初期の段階で堂々と言ってくるタイプは、一応警戒した方がいい。こういうタイプは「自分が良い人間だと思われたい」という欲求が強い。家族を引き合いに出せば好印象を与えられると経験上知っているという時点で、私としては「…なんだかなぁ」と思ってしまう。家族・恋人・友人、何にしても自分に近しい人との「親密さ」といった物は、本来、本人とその相手の両者間で承知していれば良いだけの事だ。「承認欲求」等いかにも尤もらしい言葉に振り回されて、要らぬ関心や嫉妬を買ってしまい、一番大切な「安心安全な暮らし」が疎かになっては本末転倒だと思うのだが。もちろん純粋に家族が大好きで大切に思う気持ちがあふれてしまっているパターンもなくはないが、よく知らない相手にペラペラしゃべったり、不特定多数に吹聴しまくるのは「その行動、大切にしてるように見えないんだけど」と思うのは私だけだろうか。
そして、ここからは私個人の価値観なので鵜呑みにしないでもらいたいが、私のように身近な人間関係が子供の頃に築けなかった者は、親と縁を切っていたり「産まれて来て良かったと思った事がない」タイプがかなりいるし、そのほとんどは、その事実をめったに他人に明かしたりはしない。明かさない以上、周囲の人間も知りようがない訳だが、そんな自分の苦しみを自分の中で留めておけるタイプは、基本的に他人の領分に図々しく踏み込む事もしない。相手の人間性・内面を本気で知りたいと思ったら何をしているか(どんな業績を上げて来たか)ではなく、「していない事は何か」「なぜそれをしないのか」に着目してみるのも妙案の一つだ。昔から日本人が守って来た「遠慮・謙虚・奥ゆかしさ」というのは、礼節を弁えながら、相手を尊重すると同時に、自分と身内を守る事にも繋がる一石三鳥の方法と言っても過言ではないと思う(ただし「他人と積極的に関わらない人」が「謙虚で奥ゆかしい人」とは限らない。世の中には様々な考えを持つ人間がいて、それがどういう言動に表れるかも、また様々だ)。
最悪なのは「誕生日」を誰にとっても大切で喜ばしい日という固定観念が行き過ぎて“サプライズパーティ(プレゼント)”とかをこっそり計画してしまうパターンだ。「産まれて来て良かった」と一度も思った事の無い人間に「こんなにしてもらって嬉しい。ありがとう」と同調圧力で強制的に言わせていると気付けない輩は、自分の無神経にも気付けないまま、いつの間にか「周囲に誰も居ない」という結果を招く可能性もある。
第5綴「説明と補足の続き」後半の中ほどに『「笑う」という感情について私なりに思う所がある~~~その話はまた別の機会に譲る』と書いたが、なかなか書くタイミングが見つからずにいた。これを今回の締めくくりとして書いておきたい。
私は子供の頃から漫画・アニメが好きで、その時々で色々な作品を読んだり見たりしてきたが、品質・内容ともに充実していて且つ私の琴線に触れる作品はそれほど多くはない。また子供時代にはお年玉などを遣り繰りして、かなり多くのコミックスを買い込んでいたはずだが、やはり30年ほど前は「漫画は子供が読む物」という固定観念があり、二十歳で家を出る頃までには、その大半を捨ててしまっていた。非常に後悔している。
この作品は、最初は夫が買ってきた漫画雑誌で読み始めたが、私は途中から展開が気になり過ぎて連載がまどろっこしくなり、連載終了まで我慢して、大人買いしたコミックスで読了した、という経緯のある、とても濃い内容で密度の高い、全18巻から成る逃亡・追跡劇だ(ただし面白いと感じるかどうかは個人の好みによる部分が大きく、殺人や拷問など残酷な場面もそれなりに出て来るので、気の弱い方にはお勧めしないし精神疾患持ちは読むべきではない)。
しかし私がこれから書く事は、この作品の内容そのものとは全く関係ない。因みにこの作品は主にドイツを舞台にしているが、私のドイツ旅の翌月に書く事になったのも単なる偶然・思い付きであり他意はない。
これも25~26年ほど前の話になるので、これまた記憶が曖昧なのだが、私が問題の箇所である、その作品の第11巻132頁を読んだのは、おそらく27~28歳頃だと思う。その頁では登場人物の一人がこんな事を言っている。「一番難しかったのは何だと思う?…笑い方だよ」
私が、その‘せりふ’を読むと、なぜか私の目から勝手に涙が出て来るのだ。しかし私には「悲しい・ツライ・せつない」という感情は全く無いし、そもそもこの頁は作品中の特別大きい山場でも何でもない。感情も作品の内容的にも、全く思い当たる点がないのに、どーゆー訳か、勝手に涙が流れて止まらない。初めて読んだ時は「私そんなに疲れてるのかな?」くらいにしか思わなかった。しかし気になったので、しばらくしてからまた読み返してみた。またしても涙は出て来るが、やはり感情・気持ちに変化はない。不思議に思って第1巻から読み返したり、その登場人物の、他の‘せりふ’を探して読んでみるが、特に思い当たる事はないし涙は出ない。そして、またしばらく日にちを置いてから、3回目くらいにその‘せりふ’を見返したタイミングで、またしても涙を流しながら気が付いた「登場人物も作品の内容も一切関係ない。“笑い方が難しい・笑い方が分からない”という言葉に、私の記憶の中の“何か”が反応してるんだ」
ここからが‘私’が普通の人とは一線を画する最も特徴的な部分かも知れない。どうやら世の中の大半の人々は、分からない・理解できない事があっても、差し迫った問題でもない限り、忘れてしまう場合が多いようだ。もちろん私も色々な事を山ほど忘れながら暮らしているとは思うが、この時は何かのスイッチが入ったように気持ちが切り替わった「コレはきっと私の中の何か大切な事に根差しているに違いない。ゆっくり時間をかけて、絶対に何が何でも思い出してやろう」と腹を決めた。以後は「笑う・笑い方」に関する物に注意しながら、時には第11巻を取り出してパラパラと見返したりしながら、日常を過ごすようになった。そうして半年か1年か覚えていないが、おそらく2年以上は掛かっていないはずだ。11巻を取り出す回数も数え切れなくなる頃になって、唐突に、ふっと思い出した。
――私が小学校でイジメに遭っていた時、その当時の子供の頭で思いつく限りの様々な罵り・蔑みの言葉を投げつけられていた。黒んぼ・土人・バイ菌・汚い・さわるな・近寄るな等は毎日言われていると段々慣れて来るので、さほどツラくはない。しかし何度も繰り返されると精神が壊れていくような感触のある、特別しんどさを感じる、全く慣れる事が出来ない言葉があった「オマエが笑うと気持ち悪いから笑うな」だ。
これを思い出した直後は「15年以上も前のつまんない記憶を引きずってるなんて情けない奴だな、自分」という気持ちも少しはあったが、そんな気持ちを押し潰すかのように、わくわくする歓喜・感動に近い痛快さが頭の中いっぱいに広がった。なぜなら、この記憶を思い出した途端に涙がピタリと出なくなったからだ。「こんな現象が自分の身に起こるなんて」という驚きと、人間の「記憶」と「感情」はこんなにも密接に繋がっているという発見を自分一人でしてのけたという達成感は、地味に無駄に、私に自信をつけさせた。
この時の「自分で自分を研究するって絶対面白い」という好奇心が、その後20年以上を経て自作のブログで「自分を知る」を提唱する事に繋がる等とは、もちろん当時の私は気付いていない。そして、その前段階として‘うつ病’との長く過酷な戦いが待ち受けている事にも。(←この辺でドラマとかアニメだと♪ジャジャジャジャ~ンとか効果音入る感じ・笑)
もちろん「自分で自分を研究する」などという、一見カッコ良さげな事を思い付きはしたが、実際には何をどーすれば研究できるのか、など分かるはずもないので、そのうち日常に紛れて忘れてしまった。しかしイジメについて思い返す時間は増え、「笑う」について考える習慣は、その後も数年は残った。当ブログの第1綴は、この時期にイジメについて取り戻した記憶を軸にして書いている。ここからは「笑う」について、この時期に思い出した・気付いた事を書いておく。
涙が止まったのだから正解にたどり着いたのは間違いないのだが、なぜ今頃になって?という疑問はあった。当時は結婚して数年経っており、それなりに落ち着いた暮らしは出来ているし(実際には問題は山積していたが当時の私は気付いていない・気付きたくなかった状態)、テレビを見ながら夫と会話しながら、笑う事も当たり前にやっている。イジメから解放されて10年以上経っているのに「笑う」の何が引っ掛かっているのか?
しかし改めてじっくり思い出してみると、イジメが収まった後も少なくとも「学校内」では2~3年間は本気で笑っていなかった事に気付いた。中学3年時には何人か友人も出来ていたが、私を気遣うような雰囲気の先生方に「私は大丈夫ですよ~元気にやってますよ~」的な笑い方だったように思う。そして高校に上がってからも1年程は完全に委縮していた。中学に上がった時の、あの「絶望」と「笑うな」が私の全身を占拠していた。何の屈託もなく笑った記憶が、明確にあるのは高校2年の途中からだ。
そして、そんな記憶を思い出し疑問を解消した後も「笑う」が気になり「笑う」について考えれば考えるほど、私は笑わなくなっていった。テレビを見ていても、パートで働き始めた職場内でも、愛想笑い・作り笑い・つられ笑い等、その場を盛り上げる為・取り繕う為の、道具としての「笑う」がいかに多いかを見つける度に私はうんざりした。
もちろん愛想笑い等の全てを否定するつもりはないし、無理に笑顔を作る事で、何かしらの良い変化を生む事もあるのは知っている。それでもやはり私は笑いたくない時は笑わないし、笑う時には腹の底から本気で笑いたい。大人になれば多少は嘘を吐く必要も出て来るが、自分の感情には嘘を吐くべきではない。自分を知って「本当の自分」に正直でいた方が、生きていて楽しいに決まっている。そうして私は「楽しく生きたい」という気持ちが高じた結果、人を本気で楽しませ腹の底から笑わせるにはどーすればイイのだろう、と研究するようになり、現在に至る、という訳だ。

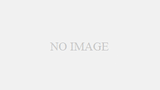
コメント